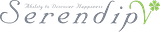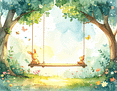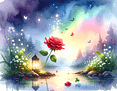自己肯定感が低いのはあなたのせいじゃない。見捨てられ不安を解放するインナーチャイルドの聖域

誰かの些細な一言で、穏やかだったはずの心の湖が、大きく、激しく波立ってしまう。
人が離れていく気配を敏感に感じ取っては、その足音が聞こえなくなるまで、必死で笑顔の仮面を貼り付けてしまう。
心の奥からは「私が悪いんだ」「もっと頑張らなきゃ、愛されない」…そんな声が、まるで止まない嵐のように鳴り響いている。
もし、あなたが今、そんな嵐の海に浮かぶ一艘の小舟のように、必死で心のバランスを取っているのなら。
どうか、覚えていてください。
その嵐は、決してあなたのせいではありません。
ただ、ずっと昔から、あなたの心の奥で泣いている小さな子が、どうしようもなく寂しくて、あなたに気づいてほしくて、必死にサインを送っているだけなのかもしれないのです。
色あせた写真の中の少女
物語の主人公を「私」と呼びましょう。
「私」はいつも、周りの期待に応えるために生きてきました。パートナーの機嫌を損ねないように、言葉を飲み込み、友人に嫌われないように、本当は疲れていても誘いを断れない。
周りからは「いつも穏やかで、優しい人」だと思われています。でも、夜、一人でベッドに入ると、言いようのない孤独感と虚しさが、まるで冷たい霧のように体を包み込むのでした。
ある静かな雨の夜、「私」はふと、実家のクローゼットの奥にしまってあった古いアルバムを手に取りました。ページをめくると、そこに写っていたのは、誕生日パーティーの隅っこで、一人だけ膝を抱えてうつむいている、幼い頃の自分の写真。
その瞬間、忘れていたはずの記憶が、鮮やかに蘇ります。
両親に褒められたくて、必死で「いい子」を演じていたこと。 本当は寂しくてたまらないのに、「お兄ちゃんだから」と涙をこらえたこと。 友達の輪から外されるのが怖くて、いつも聞き役に徹していたこと。
見捨てられるのが、ただただ、怖かった。
「私」は、はっと息をのみました。今、この胸を締め付ける「見捨てられ不安」も、自分を好きになれないこの苦しみも、すべて、この色あせた写真の中にいる小さな少女の、声なき叫びだったのだと。
彼女は、ずっと。 誰にも気づかれないまま、心の片隅で一人ぼっちで泣いていたのです。

静寂のほとり
「私」は、心の中にいるあの少女をどうにかしてあげたい、と思いました。
「大丈夫だよ、もう泣かないで」 そう声をかけてみました。でも、少女は顔を上げません。
「ほら、楽しいことを考えようよ」 無理やり笑顔にさせようとすればするほど、少女は頑なに心を閉ざし、その体は氷のように冷たくなっていきます。
そのとき、「私」は静かに理解しました。
彼女に必要なのは、正しい答えやポジティブなアドバイスではないのだと。
ただ、黙って隣に座り、彼女の震える肩をそっと抱きしめてくれる存在。 どんなに醜い感情を吐き出しても、「そうだね、つらかったね」と静かに受け止めてくれる、温かい眼差し。
評価も、否定も、ジャッジも一切存在しない。 ただ、「あなたが、あなたのままで、ここにいていい」と許される、神聖な場所(サンクチュアリ)。
もし、そんな「聖域」のような空間があるのなら。 この子はきっと、初めて安心して、心の底から涙を流せるのかもしれない。
「私」は、そう心の底から願うのでした。
答えは“外”にはなかった
これまで「私」は、安心感や自己肯定感という答えを、必死で“外”の世界に探していました。本を読み、セミナーに通い、誰かの評価の中に自分の価値を見出そうとしてきました。
けれど、本当の答えは、そんなところにはありませんでした。
本当の答えは、いつだって自分の中にいた、あの小さな少女の声に耳を澄ますことの中にあったのです。
自己肯定感とは、何かを成し遂げて自分を好きになることではありません。 何かができるから、価値があるのではないのです。
傷つき、怯え、光を失くしたようにうずくまっている、一番弱いままの自分(インナーチャイルド)。その子の存在に気づき、その冷たい手をそっととり、「もう一人じゃないよ」と伝えることから始まる、魂の約束のようなもの。
あなたが、あなたであること。 それそのものが、どれほど尊く、かけがえのない輝きを持っていることか。
その真実を思い出すための旅が、今、ここから始まります。
聖域の扉の前で

あなたの心の中にいる、あの小さな子の声。 少しだけ、耳を澄ませてみたくなりましたか?
もし、あなたがその子の手を引いて、一緒に安心できる場所を探しているのなら。
私は、その「聖域」の扉の前で、静かにあなたをお待ちしています。
無理に扉を開ける必要はありません。焦る必要も、頑張る必要も、まったくありません。
ただ、いつでもあなたと、あなたのインナーチャイルドを温かく迎え入れる準備ができている場所が、この世界にちゃんとあるということだけ。
心の片隅に、そっと置いておいてくださいね。
お話の続きは、こちらの扉の向こうで。
非日常のひとときを、あなたの心に